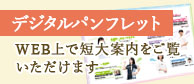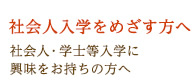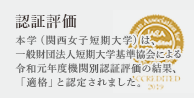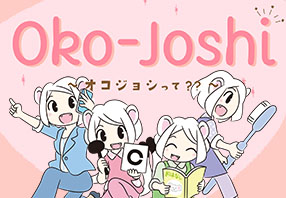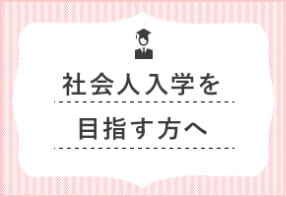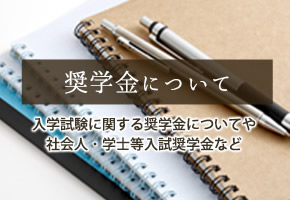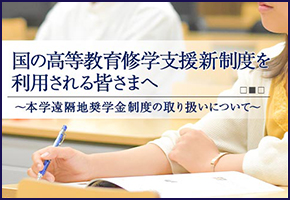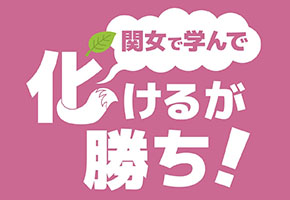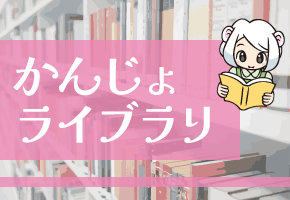歯科衛生学科
全身の健康状態をとらえた上で、口の健康づくりを支援できる、
高度な専門性をもつ歯科衛生士を3年間で養成します。
少人数制教育と実習に重きを置いた学びによって、口腔状態を総合的にとらえ、観察できる専門知識と技術を育成。
また、患者さま、社会、自分自身に対して責任をもち、広く社会に貢献できる歯科衛生士としての自覚を育みます。
関西女子短期大学のディプロマポリシー(学位授与の方針)、カリキュラム・ポリシー(教育課程の編成方針)、
アドミッション・ポリシー(求める学生像と受入れ基本方針)はこちらからご覧ください。
新着情報
歯科衛生学科 学科長 脇坂 聡 教授
口腔の健康を通して人々のQOLの向上に寄与する

歯科医療では口腔領域の疾患の治療・予防はもちろん口腔機能の維持を目的とし、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士などのチームで実施されます。代表的な歯科疾患としてはう蝕(むし歯)と歯周病(歯槽膿漏)がありますが、時代とともに疾患構造が変化し、歯科医療の考え方も変わってきています。50年ほど前は小児のう蝕が蔓延していましたが、う蝕の発症メカニズムの解明とそれに基づく治療、そしてう蝕予防指導の浸透により、現在では小児のう蝕は激変しています。
もう一つの代表的な歯科疾患である歯周病は最も罹患率の高い感染症として知られていますが、その発症メカニズムは複雑であり、十分に解明されていませんが、歯垢に存在する歯周病細菌が原因であることは明らかになっています。したがって、口腔清掃の徹底で歯周病の発症や進行を防ぐことが重要になっています。
う蝕と歯周病はそれぞれ歯と歯の周囲の病気ですが、それに加え、近年食べ物をうまく飲み込めない嚥下障害も増えてきており、現在高齢者が嚥下障害から誤嚥性肺炎になる割合が増えています。この嚥下障害の治療も歯科医療の大切な役割です。
このように歯科疾患の「治療」はもちろん、歯科疾患の「予防」、口腔機能の維持へと歯科医療は変化し、歯科衛生士の業務も変化しています。歯科衛生士は昭和23年(1948年)に制定された歯科衛生士法により歯科医師の直接の指導で歯科予防処置、歯科診療補助、歯科衛生指導などの業務を行うことが出来ましたが、平成26年(2016年)の歯科衛生士法の改正により歯科医師の判断により、必ずしも歯科医師の常時の立会いが無くても保健所や保健センターなどでフッ素塗布などを行うことが可能になりました。このことは従来に増して歯科疾患における予防処置や口腔機能の回復・維持のために歯科衛生士の果たす役割が高まったといえます。
ものを食べたり話をするという健全な口腔機能を保つということは、人間としては健やかな生活を送り、QOL(Quality of Life: 生活の質)の向上のために極めて重要です。本学では歯科衛生士として必要な知識・技術の習得はもちろん、医療人として求められる態度やコミュニケーション能力を向上させ、口腔の健康を通して人々のQOLの向上に積極的に寄与できる人材の育成を目指しています。
歯科衛生学科 学科長
脇坂 聡 教授