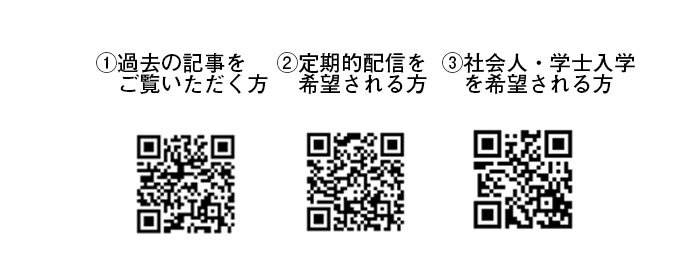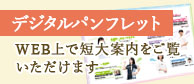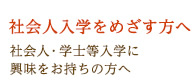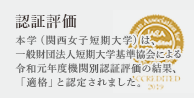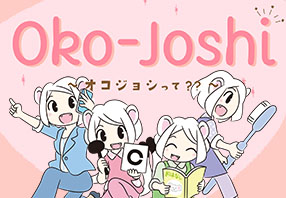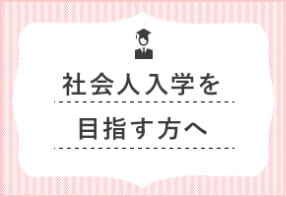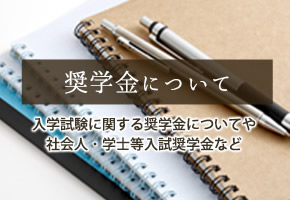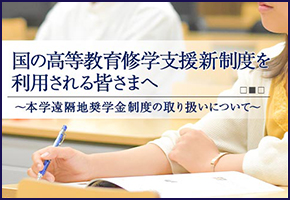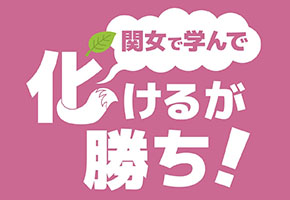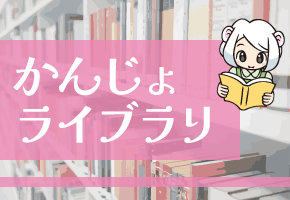養護教諭のパワースポット-関西養護保健フォーラム通信 第103号(事務局 関西女子短期大学養護保健学科)2018年11月22日
養護教諭のパワースポット-関西養護保健フォーラム通信(事務局 関西女子短期大学養護保健学科)
(ページ下部QRコード①から過去の記事をご覧いただけます。)
速報! 平成31年度養護教諭採用試験合格者15名!
(平成30年10月28日現在、卒業生を含む)
※関西女子短期大学養護保健学科では、社会人・学士入学を希望される方を
お待ちしています。2年間で養護教諭の免状が取得できます。
看護師免許をお持ちの方、大歓迎です。
これまでのあなたの「殻」を破って、養護教諭になろう!
詳細は、下記をご覧ください。
(ページ下部QRコード②からもご覧いただけます。)
養護教諭のパワースポット-関西養護保健フォーラム通信を定期購読されたい方へ
下記まで、連絡先アドレスをお知らせください。最新号が発行されましたら、メールでお知らせします。
本学卒業生以外の方のメールアドレス登録も大歓迎ですので、多くの先生方、養護教諭を目指している方に、ご紹介をお願いします。
なお、本学卒業生には一斉にお知らせしますが、迷惑メールとならないよう、端末設定をお願いします。
※連絡先アドレス送信先
(ページ下部QRコード③からも送信できます。)
関西女子短期大学 養護保健学科 yougo@tamateyama.ac.jp
※お名前、所属を必ず記載してください。
本学卒業生は、卒業年度を必ず記載してください。
名古屋大:「朝食抜くと太る」確認 体内時計や代謝乱れ
朝食を抜くと体内時計や脂質の代謝のリズムが乱れ、体重が増えることがラットの実験で分かったと、名古屋大の研究チームが31日付の米科学誌プロスワンで報告しました。
詳細は下記をご覧ください。
https://mainichi.jp/articles/20181101/k00/00m/040/185000c?fm=mnm
http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20181101_agr.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0206669
●甘い物、昼間だけならダメージ軽減
http://www.nibiohn.go.jp/eiken/linkdediet/news/FMPro%3F-db=NEWS.fp5&-Format=detail.htm&kibanID=64760&-lay=lay&-Find.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201261
発達障害の子も気軽に 宝塚にカフェオープン
発達障害のある子どもを育てる親とその支援者でつくるグループが9月、兵庫県宝塚市にカフェをオープンさせました。子どもに落ち着きがなくて店内で騒いでも、他の客の視線を気にしなくてもいい。希望すれば臨床心理士とのオンラインカウンセリングもできる。グループ代表の小林ひかりさん(35)は「『うちの子はちょっと変わってる?』と悩む親が気楽に立ち寄り、欲しい情報をもらって帰る。そんなゆるくつながれる場所になれば」と話しています。
詳細は下記をご覧ください。
自傷行為、早めに相談発達障害の可能性も
自分の頭を壁や床に激しく打ち付ける、手首や指をかむ、髪の毛を抜くといった「自傷行為」を繰り返す子どもがいる。発達障害が原因のこともあるので、子どもの状況と対応方法を知るため、早めに近くの子ども家庭センターや保健センターなどに相談したいという記事です。
詳細は下記をご覧ください。
鼻をほじってはいけないもう一つの理由
鼻をほじると自分自身だけでなく周囲の人の健康にも悪影響があることが、英リバプール熱帯医学研究所のVictoria Connor氏らが「European Respiratory Journal」10月10日オンライン版に発表した研究で報告されました。
成人の男女40人を対象としたこの研究では、鼻をほじったり、こすったりすると肺炎球菌が拡散する可能性が示された。鼻と手が接触するだけでも肺炎細菌が簡単に広がることを初めて報告したものだということです。
詳細は下記をご覧ください。
てんかんを正しく診断するために
てんかんはあらゆる年代で100人に1人程度発症する身近な病気だ。ただし約7割は治療により発作なく日常生活が送れる。つまり、てんかんは決して珍しい病気でも、治療が難しい病気でもない。しかし、てんかん発作に対する誤ったイメージが要因で、適切に診断されないことは多い。適切な診断には、まずさまざまな発作があることを知り、てんかんに対する正しい知識を持つことが重要であるとされています。
今回、こうした見落としやすい発作の理解を促す目的で、「てんかんの正しい診断をサポートするために~知っておきたい、てんかん発作のいろいろ~」と題するセミナーが都内にて開かれ、さまざまなてんかん発作の特徴などが語られました。
詳細は下記をご覧ください。
「口腔崩壊」の子ども 公立小中の5割超に<栃木>
栃木県保険医協会(長尾月夫会長)が、県内の公立小中学校に子どもの歯の状況を尋ねたところ、5割を超える学校が、虫歯が10本以上あるなど「口腔(こうくう)崩壊」と呼ばれる状態の子どもがいると回答した。虫歯が見つかっても治療しないケースも多く、学校側から「家庭の意識が低い」「部活動や塾で受診が後回しになっている」などの声が上がっているとのことです。
詳細は下記をご覧ください。
東京新聞:子どもの口腔崩壊 東京で3校に1校
虫歯が十本以上あったり、歯の根しか残っていない未処置歯が何本もあったりする状態を指す「口腔崩壊」が学校現場で問題になっています。
開業医でつくる東京歯科保険医協会が都内の小中学校を調べたところ、ほぼ3校に1校が「口腔崩壊の児童(生徒)がいた」と答えたそうです。理由は経済的困窮や、病院に行く時間がないことなどだが、子ども虐待の一つであるネグレクト(育児放棄)が強く疑われるケースもあるということです。
詳細は下記をご覧ください。