-
歯科衛生士
- 歯科衛生士になるには
- 歯科衛生士になる方法
- 給与
- 仕事内容

歯科衛生士は歯科医師の仕事をサポートし、患者さんの歯の歯垢(しこう)や歯石を取り除いたり、歯にフッ化物を塗布したりする職業です。また、患者さんの歯の健康を守るため、ブラッシングの指導や生活上のアドバイスをする「歯科保健指導」の役割もあります。歯科衛生士になるには、歯科衛生士の国家試験に合格し、歯科衛生士免許証を取得する必要があります。本記事では、歯科衛生士として働くまでの流れや、平均給与や主な仕事内容、歯科衛生士ならではの魅力ややりがいを解説していきます。
目次
歯科衛生士になるには?歯科衛生士免許証が必要!

自立した生活を送るため、歯や口腔の健康は欠かせません。歯科医師のもとで、「虫歯(う蝕)や歯周疾患など歯や歯ぐきの病気の予防処置、歯科医師の診療の補助、歯科保健指導など」の業務を担当するのが歯科衛生士です。[注1]
歯科衛生士になるには、大学・短期大学、専門学校などの歯科衛生士養成機関で専門知識やスキルを学び、卒業後に歯科衛生士の国家試験を受ける必要があります。
ここでは、歯科衛生士をめざす人向けに、歯科衛生士になるまでの流れや必要なステップをわかりやすく解説します。
[注1]厚生労働省「歯科衛生士」
歯科衛生士になるには、大学・短期大学、専門学校などの歯科衛生士養成機関で専門知識やスキルを学び、卒業後に歯科衛生士の国家試験を受ける必要があります。
ここでは、歯科衛生士をめざす人向けに、歯科衛生士になるまでの流れや必要なステップをわかりやすく解説します。
[注1]厚生労働省「歯科衛生士」
大学・短期大学や専門学校で専門知識を学ぶ
歯科衛生士になるには、歯科衛生士養成機関の指定を受けた大学・短期大学や専門学校に通う必要があります。大学・短期大学や専門学校に通う理由は、歯科衛生士法により、歯科衛生士の国家試験の受験資格が定められているからです。
高等学校を卒業後、歯科衛生士養成機関(大学、短期大学、専門学校)において、歯科衛生士として求められる知識や技術を習得し、卒業すると国家試験(歯科衛生士国家試験)の受験資格が得られます。
[引用元]日本歯科衛生士会「歯科衛生士になるには?」
なお、平成22年4月1日歯科衛生士養成機関の指定規則の改正により、歯科衛生士の国家試験の受験資格を得るには、大学なら4年、短期大学や専門学校で3年以上学ぶ必要があります。
主な歯科衛生士養成機関には、大学や短大の歯科衛生学科のほか、歯科衛生士を育成する専門学校などがあります。厚生労働省の職業情報提供サイト(jobtag)によると、歯科衛生士の87.3%が専門学校卒、36.7%が大学・短大卒(重複を含む)です。[注1]
たとえば、大学の歯科衛生学科では、口腔衛生の基礎知識や、医療従事者として必要な解剖学や生物学の知識、歯科衛生士の基礎技術や実践的なスキルを養う臨床実習などのカリキュラムが用意されています。3年次からは、病院での臨床実習が本格化し、歯科衛生士国家試験の受験対策もスタートします。大学・短期大学や専門学校によってカリキュラムに特色があるため、自分のやりたいことや学びたいことに合わせて学校を選ぶことが大切です。
[注1]厚生労働省「歯科衛生士」
高等学校を卒業後、歯科衛生士養成機関(大学、短期大学、専門学校)において、歯科衛生士として求められる知識や技術を習得し、卒業すると国家試験(歯科衛生士国家試験)の受験資格が得られます。
[引用元]日本歯科衛生士会「歯科衛生士になるには?」
なお、平成22年4月1日歯科衛生士養成機関の指定規則の改正により、歯科衛生士の国家試験の受験資格を得るには、大学なら4年、短期大学や専門学校で3年以上学ぶ必要があります。
主な歯科衛生士養成機関には、大学や短大の歯科衛生学科のほか、歯科衛生士を育成する専門学校などがあります。厚生労働省の職業情報提供サイト(jobtag)によると、歯科衛生士の87.3%が専門学校卒、36.7%が大学・短大卒(重複を含む)です。[注1]
| 学歴 | 割合 |
| 専門学校卒 | 87.3% |
| 短大卒 | 25.3% |
| 大卒 | 11.4% |
| 高卒 | 6.3% |
| 修士課程卒 (修士と同等の専門職学位を含む) |
2.5% |
| 博士課程卒 | 1.3% |
たとえば、大学の歯科衛生学科では、口腔衛生の基礎知識や、医療従事者として必要な解剖学や生物学の知識、歯科衛生士の基礎技術や実践的なスキルを養う臨床実習などのカリキュラムが用意されています。3年次からは、病院での臨床実習が本格化し、歯科衛生士国家試験の受験対策もスタートします。大学・短期大学や専門学校によってカリキュラムに特色があるため、自分のやりたいことや学びたいことに合わせて学校を選ぶことが大切です。
[注1]厚生労働省「歯科衛生士」
歯科衛生士の国家試験を受ける
歯科衛生士養成機関に指定された大学・短期大学や専門学校を卒業すると、歯科衛生士国家試験の受験資格を得られます。歯科衛生士国家試験は年1回、毎年3月初旬(令和5年度は3月5日)に実施されます。国家試験の試験を受けられるのは、北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県の10ヵ所です。国家試験は筆記試験であり、主な試験科目は以下のとおりです。[注2]
- 人体(歯・口腔を除く)の構造と機能
- 歯・口腔の構造と機能
- 疾病の成り立ち及び回復過程の促進
- 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み
- 歯科衛生士概論
- 臨床歯科医学
- 歯科予防処置論
- 歯科保健指導論及び歯科診療補助論
合格したら免許証の交付を受ける
歯科衛生士国家試験に無事合格したら、歯科衛生士として厚生労働大臣の歯科衛生士名簿に登録されます。歯科医療振興財団の指定機関で申請手続きを行うことで、免許証の交付を受けられます。
歯科衛生士国家試験の合格率は比較的高く、毎年9割以上の受験者が合格しています。たとえば、第31回歯科衛生士国家試験の合格率は95.6%で、受験者数7,416人のうち7,087人が合格しています。[注3]
大学や専門学校のカリキュラムを修了し、しっかりと試験対策に取り組めば、ほとんどの人が合格できる試験です。
[注3]厚生労働省「第31回歯科衛生士国家試験の合格発表について」
歯科衛生士国家試験の合格率は比較的高く、毎年9割以上の受験者が合格しています。たとえば、第31回歯科衛生士国家試験の合格率は95.6%で、受験者数7,416人のうち7,087人が合格しています。[注3]
大学や専門学校のカリキュラムを修了し、しっかりと試験対策に取り組めば、ほとんどの人が合格できる試験です。
[注3]厚生労働省「第31回歯科衛生士国家試験の合格発表について」
歯科衛生士として働く
歯科衛生士の免許証を受け取ったら、歯科衛生士として働くことができます。歯科衛生士の主な就職先は、歯科医院や総合病院の歯科口腔外科です。一般企業で働きたい場合は、歯科衛生士の国家資格を活かし、デンタルケアに関連したメーカーや商社でキャリアを形成することもできます。
| 職場の特徴 | |
| 歯科医院 | 歯科医院の診療補助、ブラッシングの指導、口腔ケア、フッ素の塗布など |
| 総合病院(歯科口腔外科) | 歯科医院と同様の業務に加えて、外科手術のサポートや入院者の口腔ケアなど |
| 歯科医療関連のメーカーや商社 | デンタルケアに関する商品開発や企画など |
歯科衛生士の主な仕事内容は?

歯科衛生士の主な仕事内容は、歯科予防処置、歯科保健指導、歯科診療補助の3つに分けられます。歯科衛生士の仕事というと、歯や歯ぐきにたまった歯垢や歯石を取り除いたり、歯にフッ化物を塗布したりする「歯科予防処置」のイメージがあるかもしれません。歯科衛生士には、歯科予防処置だけでなく、歯科医院の診療を補助したり(歯科診療補助)、患者さんの歯の健康を守るための生活習慣の指導を行ったり(歯科保健指導)する役割もあります。ここでは、歯科衛生士の主な仕事内容を詳しくみていきます。
歯科予防処置
歯科予防処置は患者さんの歯や口腔をケアし、むし歯(う蝕)や歯周病を予防するための仕事です。むし歯(う蝕)や歯周病は、人が歯を失う原因の90%を占めるといわれています。そのため、歯科予防処置の専門家である歯科衛生士の重要性がますます大きくなっています。主な歯科予防処置として、むし歯(う蝕)に強い歯を作るためのフッ化物塗布や、歯周病を予防するための機械的歯面清掃(歯垢や歯石、口腔内の汚れなどの除去)の2つが挙げられます。
歯科保健指導
むし歯(う蝕)や歯周病は生活習慣病の一種です。むし歯(う蝕)や歯周病を予防するには、歯や口腔を定期的に清掃するだけでなく、生活習慣を改善する必要があります。歯科衛生士には、口腔衛生の専門知識を活かし、生活上の助言やアドバイスをする「歯科保健指導」という役割もあります。とくに重要なのが、正しいブラッシングの習慣を身につけるための歯口清掃法の指導です。
また、最近は食事習慣とむし歯(う蝕)や歯周病の関係に着目し、食べ物の正しい食べ方や噛み方を指導する「食育支援」の重要性も高まっています。老人福祉施設などでは、高齢者や要介護者の摂食・嚥下機能訓練(嚥下体操)を歯科衛生士が担当することもあります。
また、最近は食事習慣とむし歯(う蝕)や歯周病の関係に着目し、食べ物の正しい食べ方や噛み方を指導する「食育支援」の重要性も高まっています。老人福祉施設などでは、高齢者や要介護者の摂食・嚥下機能訓練(嚥下体操)を歯科衛生士が担当することもあります。
歯科診療補助
近年の歯科診療は、歯科医師や歯科衛生士が協働するチーム医療の側面があります。歯科医師の指示を受け、歯科診療を補助するのも歯科衛生士の大切な役割のひとつです。そのため、患者さんとの円滑なコミュニケーションや、歯科医師が治療しやすくするための気配りなども歯科衛生士に求められます。歯科医院によっては、経験を積んだ歯科衛生士が歯科インプラント治療を担当する場合もあります。
歯科衛生士の給与はどのくらい?どんな人に向いている?
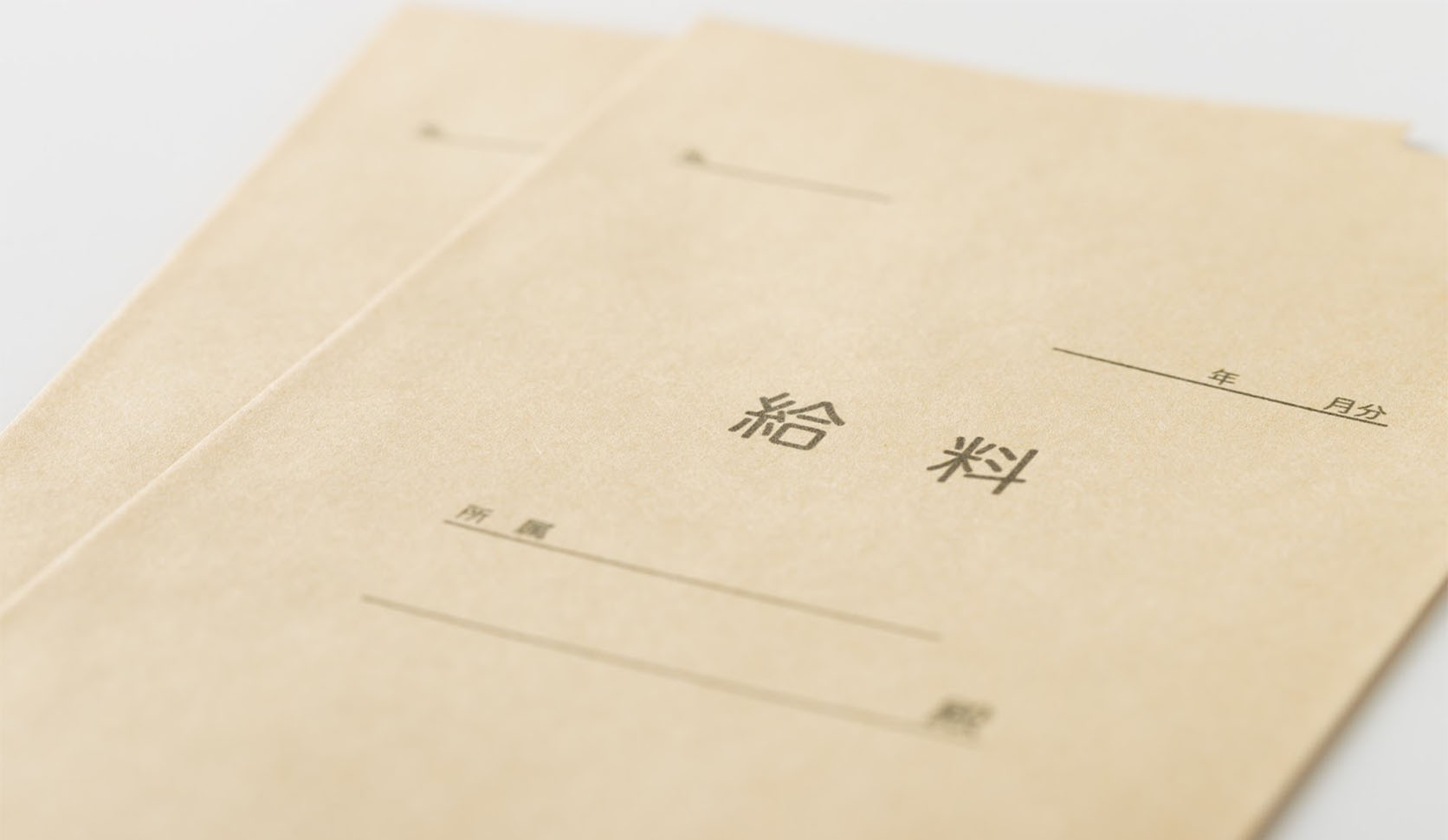
歯科衛生士になると、どのくらいの給与がもらえるのでしょうか。ここでは、厚生労働省の令和4年賃金構造基本統計調査を元にして、歯科衛生士の平均給与(所定内給与)や年間賞与、歯科衛生士に向いている人の特徴を解説します。[注4]
[注4]厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査 ※職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
[注4]厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査 ※職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
歯科衛生士の給与はどのくらい?
令和4年賃金構造基本統計調査によると、歯科衛生士の給与の平均は約271,300円、年間賞与の平均は約432,300円です。年収に換算すると、歯科衛生士の平均給与は約3,687,900円となります。
次に、歯科衛生士の平均給与を年齢別にみてみましょう。
もっとも平均給与が高いのは60~64歳の年齢区分ですが、45~49歳の年齢区分も2番目に高くなっています。歯科衛生士の給与水準は、40歳代にかけて少しずつ上昇し、それ以降は60~64歳まで横ばいの傾向にあります。
次に、歯科衛生士の平均給与を年齢別にみてみましょう。
| 年齢区分 | 所定内給与額 | 年間賞与 その他特別給与額 |
| 20~24歳 | 234,300円 | 165,800円 |
| 25~29歳 | 262,700円 | 484,600円 |
| 30~34歳 | 264,300円 | 305,100円 |
| 35~39歳 | 283,400円 | 440,300円 |
| 40~44歳 | 293,800円 | 842,000円 |
| 45~49歳 | 300,400円 | 442,700円 |
| 50~54歳 | 295,900円 | 605,100円 |
| 55~59歳 | 267,800円 | 651,500円 |
| 60~64歳 | 327,000円 | 502,100円 |
| 65~69歳 | 277,200円 | 796,700円 |
もっとも平均給与が高いのは60~64歳の年齢区分ですが、45~49歳の年齢区分も2番目に高くなっています。歯科衛生士の給与水準は、40歳代にかけて少しずつ上昇し、それ以降は60~64歳まで横ばいの傾向にあります。
歯科衛生士に向いているのはどんな人?
歯科衛生士に向いている人の特徴は以下のとおりです。
- コミュニケーション能力が高く、患者さんと良好な関係を築くことができる人
- 細かな作業が得意で、歯科予防処置などのスキルが高い人
- 協調性があり、歯科医師の指示を受けてしっかりと仕事をこなせる人
- 向上心があり、歯科予防処置や歯科保健指導のスキルを積極的に学べる人
歯科衛生士の魅力は?

歯科衛生士の魅力ややりがいは、大きく分けて3つあります。
- 幅広い場所で働ける
- 専門知識を活かして働ける
- 結婚や出産後も続けられる
幅広い場所で働ける
歯科衛生士は幅広い職場で活躍できる職業です。一般歯科や総合病院のほかにも、介護保険施設や老人福祉施設、歯科医療関連のメーカーや商社などで働く人もいます。また、大学で歯科衛生を学んだ人は、そのまま大学院に進学し、研究者として専門研究に従事することも可能です。歯科衛生士の有効求人倍率は22.6倍(2021年)と非常に高く、需要が高い職業でもあります。[注5]
[注5]日本歯科衛生士会「歯科衛生士6つの魅力」
[注5]日本歯科衛生士会「歯科衛生士6つの魅力」
専門知識を活かして働ける
歯科衛生士は、国家試験の合格が必要な歯科衛生のスペシャリストです。大学や専門学校で学んだ専門知識やスキルを活かし、歯科衛生士として一生働くことができます。生涯にわたって安定したキャリアを求める人は、歯科衛生士をめざしましょう。
結婚や出産後も続けやすい
歯科衛生士は結婚や出産後も続けやすい職業のひとつです。日本歯科衛生士会によると、歯科衛生士の39.0%は非常勤で働いています。復職支援が充実した歯科医院も多く、出産や育児、介護などと両立しながら働くことが可能です。また、歯科医院は日本全国に67,741施設もあり、全国どこでも働けるため、転居・引越し先でもすぐに仕事を見つけることができるでしょう。[注5]
[注5]日本歯科衛生士会「歯科衛生士6つの魅力」
[注5]日本歯科衛生士会「歯科衛生士6つの魅力」
歯科衛生士の仕事内容を把握して自分に合った学校を選ぼう
歯科衛生士は歯科医師の業務を補助し、患者さんの歯の健康を守る職業です。歯科衛生士になるには、歯科衛生士養成機関の指定を受けた大学・短期大学や専門学校で学び、歯科衛生士の国家試験に合格する必要があります。歯科衛生士免許証を取得すれば、歯科衛生に関する専門知識を活かし、一般歯科や総合病院など幅広い場所で働くことが可能です。
歯科衛生士をめざせる大学なら、関西女子短期大学の歯科衛生学科がおすすめです。歯科衛生学科では、歯科衛生士の国家資格の受験資格が得られるだけでなく、社会福祉主事の任用資格も取得できます。歯科衛生学科の就職率は98.9%(2021年5月1日時点)で、ほとんどすべての学生が一般歯科や総合病院で活躍しています。これから歯科衛生士をめざす人は、関西女子短期大学の歯科衛生学科で専門知識を学びませんか。
歯科衛生士をめざせる大学なら、関西女子短期大学の歯科衛生学科がおすすめです。歯科衛生学科では、歯科衛生士の国家資格の受験資格が得られるだけでなく、社会福祉主事の任用資格も取得できます。歯科衛生学科の就職率は98.9%(2021年5月1日時点)で、ほとんどすべての学生が一般歯科や総合病院で活躍しています。これから歯科衛生士をめざす人は、関西女子短期大学の歯科衛生学科で専門知識を学びませんか。
この記事を書いた人

所属:入試広報部
おこじょ5号
「専門職に興味がある」方に向けて、わかりやすく「お仕事」の情報をお届けできるよう頑張ります!



